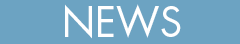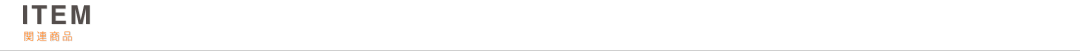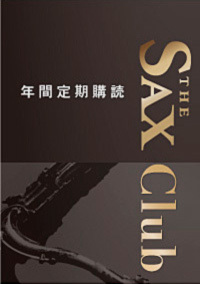本誌表紙&巻頭を飾ったボブ・ミンツァー氏が愛用する楽器、EASTMAN(イーストマン)だが、近年日本でも再び注目を集めている。ヴィンテージの銘器「マークⅥ」、「Super Balanced Action(以下SBA)」を徹底的に研究したというイーストマンを今回試奏検証してくれたのは、モントリオール国際ジャズフェスティバル出演など、国内外で活躍するジャズプレイヤーの碓井雅史氏。学生時代の恩師・雲井雅人氏との出会いからマルセル・ミュールの音色に傾倒するクラシカルなバックボーンを持つ一方で、古き良きジャズ、とりわけその“音色”に強いこだわりを持つ碓井氏。ヴィンテージ楽器にも造詣が深い氏の厳しい目線から、この楽器の実力に迫る。
●PROFILE
碓井雅史 Masashi Usui
サクソフォーン奏者、作編曲家、MARCA Reeds Saxophone Gold Artist日本第一号。
富山県出身。愛知県立芸術大学器楽科卒業。McGill大学大学院音楽学部jazz performance科を日本人第一号として修了。同大学院よりSchulich ScholarshipおよびGraduate Excellence Fellowshipを付与される。1998年第15回富山県青少年音楽コンクール「青少年音楽大賞」など歴代最高数の賞を受賞。2016年モントリオール国際ジャズフェスティバルに自身のカルテットで出演し、以降同フェスティバルの常連として名を連ねる。これまでに数多くのライブ、レコーディングを行なっており、Reg Schwager、Paul Shrofel、Adrian Vedady、André White、Laura Anglade、Fernanda Cunhaといったカナダの著名アーティストらとともにアルバムをリリースする。音楽家育成にも才能を発揮しており、モントリオール国際ジャズフェスティバル40周年記念として開催されたOliver-Jones Awardにて彼の生徒がグランプリを受賞。2018年までMcGill大学講師(Jazz Practical Instruction)。クラシック奏法とジャズ奏法の往来および両立に関する研究分野のパイオニア。
公式Website https://usuimasashi.com/
碓井
アルト・テナーともに、コーンのニューワンダー1をメインで使っています。ニューワンダーは1と2があるのですが、僕が使っているのは1920年製造、金メッキ仕上げの7万番台ぐらいの「アーティストスペシャル」といって彫刻が一点彫りのもの。木管的なとても柔らかい音が特徴で、アドルフ・サックスの系譜を体感できます。僕はこのニューワンダーの音色の質感が好きで使っています。
碓井
ジャズにスイッチして最初に手にしたアルトはセルマーのマークⅥの13万番台でした。中期のモデルで、どちらかといえばちょっと明るめの音色。その後、コーンの10Mの状態のいいテナーを譲ってもらえる機会があり、吹いてみたら「すごい音がするぞ」とそこからコーンの音色に惹かれました。そしてチャーリー・パーカーも使っていたアルトの6Mを探すようになり、その際にニューワンダーも吹き比べてみたら、「あれ? ニューワンダーのほうが好きだぞ」と(笑)。18年ほど前ですが、それ以来ずっと使っています。
碓井
色々試しましたね。セルマーのSBAやマークⅥはもちろん、キングのスーパー20やゼファーモデル、ブッシャーやマーティンなど一通り吹きましたが、やっぱり音色の質感が違うなと。
操作性は10段階評価の10
―
そんな碓井さんが今回試奏されたイーストマンサックスは、ヴィンテージサックス、特にマークⅥやSBAを研究して作られたモデルと聞いています。実際に吹かれた感想は?
碓井
音色でいえば、いわゆる本物のヴィンテージとはまだ「似て非なる音」という部分はあります。ただ、今回イーストマンを試奏する中で、特にネックにいい意味での個体差がしっかりあり、マウスピースとの組み合わせによって、SBAや初期のマークⅥのエッセンスを強く感じた個体がありました。これって結構すごいことだと思います。少なくともこれまでに僕が試してきた現行のモデルでそう感じたサックスは正直なかったので。
個人的に「音の中毒性」を10段階評価で表すなら、ニューワンダー1GPは抜群で10。後継モデルのコーン6Mなら7ぐらい。マークⅥも同様に機能性が上がる分、音色で削がれる部分が出てくる。でもこれが操作性になるとマークⅥは10段階の10と圧倒的に扱いやすい。ニューワンダー1の操作性はせいぜい3か4ぐらいです(笑)。
―
操作性とはキィアクションのことですか? それとも音程やイントネーションも含む?
碓井
キィアクションやオクターブの機構ですね。マークⅥはシンプルで良くなってますよね。逆に音程やイントネーションは、マウスピースとの組み合わせがマッチすれば解消されるので、その違いはあまりないです。
碓井
この楽器はマークⅥを研究しているからか、操作性でいえば10段階の10のところに行きますね。
碓井
はい。触った感じはマークⅥに近いというか、正直ほとんど変わらないレベルです。「よくできてるなぁ」というのが第一印象でした。
―
ひと昔前の中国製や台湾製の楽器は造りが大ぶりなものもあって、日本人で特に手が小さい人には操作が難しい印象もありましたが、そうではないんですね。
碓井
それは全然感じなかったです。もしかしたら僕が普段、操作性3の楽器を使っているからかもですが(笑)。普段マークⅥをシビアに使ってる方ならまた違った意見になるかもしれない。それでも大きな差は感じず、むしろSBAや初期のマークⅥに音色が近いと思ったイーストマンの個体は、握ったときの右手のサイドキィの距離感や触った感覚もSBAやマークⅥに近かったです。そういう良い意味での個体差を特にネックに感じたので、もし可能ならば、選定してみても良いかもしれません。
メジャーブランドと比較しても有利
―
ゴールドラッカーとノーラッカーの2種類がありますが、音色の違いは?
碓井
最近の楽器でもノーラッカーは増えていますが、その理由はマウスピースです。現在出回っている現行マウスピースは今の楽器の設計に合わせて作られていて、例えば現行のメイヤーやオットーリンクはヴィンテージのものに比べて輪郭がはっきりしていて、音がスパーンと出る印象です。だからメッキやラッカーが乗ってる楽器に使うと、角の立ったエッジィな音が拡張されて、ジャズだとちょっとキツい音になりやすい。それがノーラッカーの楽器だと、ほどよくその角を落としてくれて、柔らかい音にしてくれる印象です。
―
なるほど、マウスピースとのマッチングでも変わるのですね。
碓井
変わりますね。おそらく今発売されてる現行マウスピースをメインにされてる方は、イーストマンならノーラッカーのほうが合うのではないかと思います。逆に、ヴィンテージマウスピースを使っている方は、ゴールドラッカーのほうがマークⅥやSBAに近いと感じると思います。
―
碓井さんはゴールドラッカーの方が合っていると感じた?
碓井
僕が普段アルトで使っているマウスピースは、1940年代くらいのセルマーのエアフローというヴィンテージマウスピースなので、ゴールドラッカーの方が断然結果が良かったです。これが後継モデルのセルマーソロイストを使っていたら結果はわからないですね。ピリッとした成分が入ってくるので、ノーラッカーのほうが合うという人もいるかも。
碓井
音色はアルトと同じ傾向ですね。テナーは試した本数が少なかったのですが、操作面ではSBAやマークⅥと同じ感覚で扱えたので、メカニック面はやはりすごく評価できる点ですね。
―
テナーはETS652の上に、ボブ・ミンツァー シグネチャーモデルETS852がありますが、その違いは?
碓井
ミンツァーはフレディ・グレゴリーのマーク1か2を使っていたんじゃないかなと思うのですが、チェンバーの容積がちょっと狭めで比較的明るい音色。ジャズだけに限らずファンクやフュージョンにも合うマウスピースなので、そこに合わせて作られた楽器だと感じました。僕は、ブリルハートのトナリン・ストリームラインをメインで使っていて、チェンバーの容積が広めなマウスピースなので、音程感で多少ミスマッチを感じました。ただ逆に652モデルを吹いたときには噛み合ったので、選ぶマウスピースの違いかなと思います。ミンツァーの音が好きで、似たセッティングで吹きたい方にはど真ん中にくる楽器ですね。
キィは全体に形状が652とは違っていて、設計的にもかなり手を加えられており、より操作性を追求しているように感じました。
―
碓井さんは、クラシックとジャズ両方の経歴をお持ちですが、この楽器はどういう人に向いていますか?
碓井
僕が普段アルトで使用しているマウスピースはそんなに開きがない、クラシックの方でも吹けるマウスピースなのですが、このセッティングだとクラシックも吹けると思いましたね。それにマークⅥといっても、実はあまり良くない個体もあったりするんです。ヴィンテージ楽器にはそういったリスクもあるので、ヴィンテージを買うのは怖いけど、初期のマークⅥを探している方は、イーストマンの楽器ならうまくマッチするかもしれません。
―
新興メーカーにとってクラシックは参入が難しい市場でもありますが、クラシックでも使えると?
碓井
面白いと思います。幅が広い楽器だと感じたので、吹奏楽の方もぜひ試してみてほしいです。
碓井
音色の面ですね。メジャーブランドの最上位クラスと比較しても、イーストマンでマウスピースやリードのセッティングがうまく噛み合った個体の方が、もっと柔らかい音色のものを選べるかもしれない。音に柔らかさがあるって、実はとても有利なんですよ。音には色々な形がありますが、柔らかい音は基本的に球体的で放射状に響く3Dのイメージ。逆に鋭い音は角が立って、プロジェクションも上がる2Dのイメージで、イーストマンは前者。“角”を落とすのは大変だけど、ないところに角をつけるのは割と簡単なんです。いまだにマークⅥやSBAを使う人が、現行の楽器に移れない理由はそこなんですよね。どうしても角が 出てしまい音が硬く痛く感じる。
例えばタイトな鋭いセッティングでファンクを吹くとちょっとトゥーマッチになる。メイシオ・パーカーが、ヴィンテージの楽器にブリルハートを使うのもそういうところですよね。バキーンと吹いてもそこまでキツい音にならない。ジャズやポップスで、デュコフのようなスモールチェンバーのメタルマウスピースを使ってる人だと、イーストマンのゴールドラッカーは鳴りすぎてキツいと思いますが、ノーラッカーで合う個体を見つけられれば面白いと思います。
高騰するヴィンテージ市場に向けた新たな選択肢
―
お話を伺うとマイナス要素がない楽器のように感じましたが?
碓井
それでも音色的には「似て非なる音」ではあります。プロの奏者であれば誰でもそうだと思いますが、僕も音色や音像にはとてもシビアなこだわりを持っているほう。でもちゃんとヴィンテージの銘器と並べて評価できる土俵に入っていて、かつメジャーブランドの現行の最上位機種と比べてもヴィンテージに近づける可能性があるってかなり凄いことだと思います。
プロ奏者ですでにベストな楽器を持っている人に向けた楽器ではないですが、いい状態のヴィンテージが市場に出回ることが年々減っていて、値段も高騰している現状なので、特に愛好家の方や学生さんには一度試してほしい楽器ですね。
―
やはり、いい状態のヴィンテージは減っていると?
碓井
減っていますね。僕は自分自身も含めてですが、お弟子さんだったり、友人の奏者だったり、関係者でヴィンテージを探してる人も多いので、年間で10本以上はヴィンテージ楽器を購入するんです。だから海外市場に出回っているものも常にチェックしていて、バイヤーからの入荷情報も入るのですが、例えばキングのスーパー20でいえば、18年で20本以上試してきましたが購入に至ったのはゼロ。状態のいい楽器が市場に出回る数自体減っているのに需要はむしろ増えているから値段も高騰していて、半年前にアメリカの楽器屋さんでミントコンディションのマークⅥで6万番台のものが2万8000ドルでした。日本円にしたら450万円前後です。恐ろしいですよね(笑)。
―
試奏されてみて、新興メーカーへの印象は変わりましたか?
碓井
変わりました。メーカー名を気にしないで、メジャーブランドと並べてブラインドでぜひ吹いてみてほしいと思いました。このメーカーはマークⅥやSBAを3Dスキャンしたデータをしっかり取って、細部まで研究している。キィカップも角を削って磨いたラウンドシェイプになっていますが、これもマークⅥの特徴。こういった部分も音に影響があると思います。細かいところまでちゃんとしているから、今後にも期待が持てますよね。セルマーだけじゃなく、僕のようにアメリカンヴィンテージの音色が好きな人も多いので、コーンも出してくれないか直談判しに行ってみたいですね(笑)。