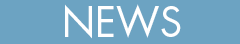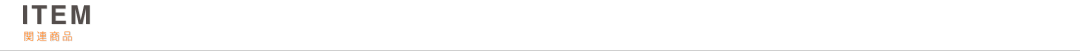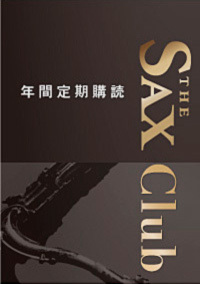お手入れ術&メンテナンス法の新常識
『The SAX』読者の皆さまは愛器の日々のお手入れをどのようにされているだろうか。スワブを通し、タンポの水分を取り、分解してケースにしまうという毎回繰り返すお手入れ、そのやり方に間違いはないか? 意外とわからないところもあるだろう。今回の特集では、石森管楽器の石森信二氏と、ヤナギサワ・クロッシュの山田敬三氏という日本有数のサックスのプロフェッショナルお二人に、メンテナンスに関する大小様々な質問をぶつけてきた。
(取材・文:渡部祐也/インタビュー・取材:ねじ助/取材協力:株式会社石森管楽器、サックス工房 ヤナギサワ・クロッシュ)

株式会社石森管楽器
1951年に石森管楽器修理所として石森善吉が創業した、70年以上続く管楽器専門店。
石森信二氏は先代実氏の次男として、1983年の入社以来修理技術の継承とともにウッドストーンブランドでのリガチャー、リード、マウスピースそしてサックス本体といった各種商品の開発に携わっている。
住所:〒169-0073 東京都新宿区百人町1丁目20-23
TEL
ショールーム:03-3360-4970
修理部:03-3360-9888
FAX:03-3360-4590
MAIL:info@ishimori-co.com
URL:https://www.ishimori-co.com

サックス工房 ヤナギサワ・クロッシュ
サックスメーカー・ヤナギサワが「ご愛用の楽器を長く、良い状態でお使いいただくために運営する」修理工房。
山田敬三氏は1983年に柳澤管楽器株式会社へ入社。工場取付部にてサクソフォンの製造に携わる。1990年に修理部へ異動。1995年に修理部のみ現在の新宿へ移転し、ヤナギサワ・クロッシュとしてオープンし、現在に至っている。
住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-4 アコード新宿201
TEL:03-5269-3417
FAX:03-5269-3418
URL:https://www.yanagisawasax.co.jp/maintenance.html
Q1
Q1 スワブの通し方を教えて!
石森 スワブは可能ならば本体用とネック用をそれぞれ準備しましょう。本体用は弊社のボディスワブのようにスポンジが入っているものがおすすめです。U字管の一番下の部分に唾が溜まるのでそこにスワブを通したいわけですが、通常のスワブだと通すときに細くなってしまい、U字管の上部ばかりを拭いてしまうことになり、効果が薄くなってしまいます。スポンジが入っていることでU字管の下部までしっかり水分を拭き取ることができるようになるのです。またガーゼ素材なので吸水性がよく、万が一管体に引っかかったとしてもキィなどを曲げてしまう前にスワブが破けるようになっています。
ネック用のスワブも弊社のものがあります。逆側にもひもをつけているので、万が一引っかかった時も反対に引っ張ることで取り除くことができます。
スワブを通すときはベル側から入れ、往復させずに抜き切ってしまうことをおすすめします。そのほうが上部の管に溜まっている水分をあまり移動させずに出すことができます。ネック用のスワブが手元にないなどスワブを抜き切ることができない場合は、できるだけゆっくり通すことでスワブに水分を染み込ませてから抜くようにするとより効果的に水分を取り除くことができます。
U字管の底にゴミが溜まってしまっている楽器は中古の楽器でよく見かけます。夏になるとそこにカビが生えてしまうことになります。楽器を吹く時は息を吐くだけではなく吸うわけですから、清潔に保ちたいですね。


 ネックのスワブの通し方
ネックのスワブの通し方 Wood Stone ボディスワブ
Wood Stone ボディスワブ Wood Stone シルキースワブ
Wood Stone シルキースワブ
山田 スワブは、通す前に必ず広げて伸ばした状態にしてから、通すようにしてください。結び目がある状態で通そうとすると引っかかってしまうので絶対にやめましょう。また、紐の部分に玉ができていると紐の長さが短くなり通しにくくなってしまうので、解いてから通すようにしたほうがいいと思います。
さらに、ネックと本体との接続部もしっかり水分を取るようにしてください。ここは真鍮が剥き出しの部分なので、放っておくとすぐに緑青が出てしまいます。そうなると本体とネックが噛んでしまいスムーズに抜き差しできなくなってしまうので要注意です。