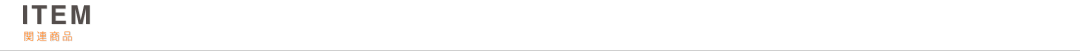(左から)内海さん、佐藤さん、藤井さん
(左から)内海さん、佐藤さん、藤井さん発売から40年以上の時を経て、いまもなお愛され続けるサクソフォン、それが「ヤマハ62シリーズ」だ。
本誌110号、111号で紹介してきた『YAS-875EX』『82Z』など「ヤマハカスタムシリーズ」の源流でもある62。その誕生から、現行品である第4世代までの開発にスポットを当て、なぜこれほど長い間多くのプレイヤーを魅了しているのか、その秘密を探る。お話を伺ったのは、初代62の設計を務めたヤマハOBの佐藤総男さん、そして現在サクソフォン開発に携わるヤマハB&O開発部の内海靖久さんと藤井駿さん。3名の視点で、開発の歴史を辿っていく。
文:鬼木玲子/写真:井村重人(アーニーズ・スタジオ)
協力:ヤマハ株式会社、株式会社ヤマハミュージックジャパン
図面化によって大躍進した61シリーズの誕生
62シリーズの話に入る前に、語るべきシリーズがある。それは、1967年に発売された「61シリーズ」だ。ヤマハサクソフォンの歴史は、ここから始まる。佐藤さんが入社した1966年には、既にその開発が終盤に入っていたという。
佐藤
61シリーズのアルトとテナーで私が担当したのは、キィガードなどの管体付属部品の設計です。そして、アルトとテナーが発売後、私が主担当になってソプラノとバリトンの開発をスタートしました。設計の図面化に着手したのも、61が初めてのことでした。それまでの図面と言えば、A0かA1くらいの大きなサイズに書かれた物が数枚ある程度。大雑把でしたね。これでは上手くいかないだろうとなり、他の楽器担当者とも協力しながら、仲間と一緒に図面を書くことに。部品図、組み立て図、完成図など一式を図面化しました。ところが、図面通りに作成した部品を実際に組み立てていくと、合わないところが出てくる。微妙な誤差が生じるので、それを見つけて修正するのが大変でした。部品が出来たら測定して、また図面化する。その図面をもとにまた作成して、測定するということの繰り返し。これには苦労したけれど、やはり図面化は大きな一歩だったと思います。
61シリーズの改良には、フランスのギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団で活躍していたミッシェル・ヌオー氏が関わっている。当時、彼はセルマー社の顧問になる予定があり、その契約前に少しでもと協力を仰いだ。少ない時間の中で、低音域の音程、キィの形状、メカの連結部などの改良に関するアドバイスを受けたそうだ。いち早く世の中に出そうとスピードが求められる中で、ソプラノからバリトンまで全シリーズを4~5年の間に発売するという目標を、佐藤さんたち開発者はやり遂げた。
佐藤
アルトとテナーに続いて2年後にバリトンが、さらに1年後にソプラノが発売されました。従来のサクソフォンに比べて運指メカが格段に良くなり、ヤマハが管楽器製作に本格的に参入した第1弾としては、まずまずの出来になったと思います。一方で、吹奏感や音色に関しては、まだ何か足りないと感じていました。その原因が、当時はなかなか掴めませんでしたが、後に62シリーズを開発していくにつれて、だんだんと分かってきたのです。
 1967年当時のヤマハ管楽器設計部門の様子
1967年当時のヤマハ管楽器設計部門の様子ルソー氏が求めるスタンダードな楽器を目指して
一段落したのが1972年。その年の後半には、アメリカを代表するサクソフォン奏者ユージン・ルソー氏がアドバイザーとなり、61のフルチェンジアップを目指すことになった。
佐藤
61がベースではあるけれど、まったく新しい開発にしようと設計も一新しました。特に吹奏バランスの改善や運指メカ、そして外観デザインも含めてスタンダードとなる楽器を目標に掲げました。ルソーさんからは、「良好な音程・鳴りの均一・演奏を妨げないメカニズム」を求められました。「音の3要素となる《音程(Intonation)・アンブシュア(Embouchure)・息(Air)》の相関関係を崩さない楽器が必要である」というルソーさんの考えを知り、一理あるなと思いました。
さて、具体的にはどんな点を改良していったのだろうか。
佐藤
まずは、管体の見直しです。吹奏感や音程に直接関わるので、最後までじっくり検討しました。テーパー(管の広がる角度)の形状も、ほんの僅かな違いですが、新しいものになりました。そして、材料。真鍮の配合や加工具合を見直しました。適切と思われる配合を精錬メーカーに打診しましたが、受け入れてもらえないことも。管楽器材料の市場はとても小さいので、他業界の工業規格に合わせなくてはならなかったのです。やむを得ず、ギリギリのところで65:35(銅:亜鉛)の配合に落ち着き、硬度やグレインサイズ(金属の結晶粒度)を指定しました。
また、ヤマハ独自の加工法である「音響焼鈍」が施されたのも、62シリーズが初である。
佐藤
音響焼鈍は、温度と時間の設定で大きく音が変わります。ベストな組み合わせにたどり着くまでには、2~3年、いや、4~5年かかったかもしれません(笑)。特に、冷却具合が難しかった。瞬間的に冷やすのはどうかという検証もやりました。最終的には、現在も行なわれている時間をかけての冷却(徐冷)に落ち着きました。
さらに、ルソー氏が最もこだわっていた音程に関しても、時間をかけて開発した。
佐藤
IBMの大型コンピューターを使っての音程計算が、1回に40分程度かかるのです。これは本当に面倒でした(笑)。現在は、数分で終わりますからね。この音程計算を最低でも5~6回行なって、OKとなったところでルソーさんに試奏していただきました。プレイヤーによっては、楽器を吹く際にご自身で音程を補正してしまうのですが、ルソーさんは決してそのようなことはありませんでした。ご自分の吹奏状態を変えることなく、常に一定にして判断してくださったことが、62最大の武器とも言える「正しい音程が得られること」に繋がったと思います。
 ヤマハサクソフォンの製品チェックを行なうルソー氏
ヤマハサクソフォンの製品チェックを行なうルソー氏 ブラインドホールドテストで試奏するルソー氏
ブラインドホールドテストで試奏するルソー氏
次のページへ続く

 (左から)内海さん、佐藤さん、藤井さん
(左から)内海さん、佐藤さん、藤井さん 1967年当時のヤマハ管楽器設計部門の様子
1967年当時のヤマハ管楽器設計部門の様子 ヤマハサクソフォンの製品チェックを行なうルソー氏
ヤマハサクソフォンの製品チェックを行なうルソー氏 ブラインドホールドテストで試奏するルソー氏
ブラインドホールドテストで試奏するルソー氏