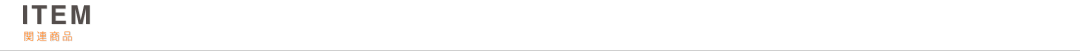チャーリー・パーカーのすべて
楽器セッティングの変遷と考察 Parker’s Setting Transition
チャーリー・パーカーの楽器やセッティングに関しては、さまざまな逸話が存在するが、ここでは彼の歴史の流れに沿って、 その変遷がどうであったのか、当時の資料や音源から考察していこう。(文:渥美順平)
代表的な使用楽器とマウスピース

KING SUPER20

C.G.Conn 6M

Brilhart Tonalin

Brilhart Streamline
※撮影はテナー用
34歳という若さで世を去っているためチャーリー・パーカーの活動期間は短いが、20歳の頃にはジェイ・マクシャンのバンドで既に名声を得ていたという。そのマクシャンとともに活動した頃、楽器はHoltonやC.G.Connの6M(上写真)等を使用していたようだ。マウスピースはOtto Linkで、ラバーのReso ChamberやメタルのMaster Linkであると思われる。当時の録音ではラージチェンバー※に由来する柔らかな芯を持つ音色ながら、バンドの中で埋もれないサウンドや抜群にキレの良いフレーズを聴くことができる。
その後ディジー・ガレスピー、マイルス・デイヴィスらと共にビバップ~モダンジャズ創成期においてその中心人物として人気を不動のものにしていくが、その頃の楽器はMartinのHandcraft、C.G.Connの6M、H.SelmerのModele26が見られる。マウスピースはBrilhartのTonalin、Streamlineが多く使われていたようだ。それまでのラージチェンバーのマウスピースからセッティングを大きく変え、アンサンブルの中でさらに際立ったサウンドと、ビバップの高速フレーズに追従するスピード感のあるキャラクターを押し進めていったのかもしれない。Streamlineは、Tonalinと同じ素材でやや細身に作られているため、通常のTonalinより重厚感はないが、レスポンスは速くブライトでハスキーな成分が強めのマウスピースである。
1940年代後半になると、それまでのドラッグや不摂生がたたり入院をするほど体調を崩したようだが、この時期に2度のヨーロッパツアーに出たり、その間にストリングスとのレコーディングをするなど、亡くなるまでの数年間もかなり精力的に活動している。この頃の楽器はKingのSuper20(上写真)、H.SelmerのNew Large BoreとBalanced Action、Graftonなどが使われているようだ。マウスピースに関しては、フランスのツアー中にBerg Larsenのラバー、帰国後のストリングスの録音やそれ以降はSelmer Englandと思われるメタルマウスピースの使用が多く見られる。いずれもチェンバーはやや小さめで、バッフルも少しあるため、それまでよりブライトな音色の出るセッティングだ。そのストリングスとの録音の中でパーカーの音色は以前にも増し、突き抜けて輝かしく聴こえる。サックスの音色だけを聴くとその音色からは時代に見合わないハイファイな録音かと錯覚するが、バックの管弦楽器の音色はあまり高域の成分が多くはなく落ち着いて聴こえるので、当時の生音はさらにキラキラとした倍音をまとっていたのではないだろうか。
BrilhartのTonalinはかなり多くの演奏に使われていたようだが、その素材自体は脆く、他のメーカーのマウスピースに比べ内径も細かったためにシャンク※にクラックが入りやすく、現代に残された40年代のBrilhartもその多くにクラックが見られる。パーカー自身、楽器本体を替える頻度が高いせいもあるが、その度にその問題を気にしなくてはならないことがマウスピースを替えるきっかけのひとつであったのかもしれない。ちなみに1930~40年代のH.Selmer等のマウスピースは内径がかなり太く、楽器のネックコルクも太かったので、コルクを細く削るなどしないとStreamlineでは試奏できなかったと推測される。
現代に残されたパーカーの録音はすべてにおいて一聴して彼だと分かる音色とフレージングに彩られている。それが何に由来するものなのかと、使用された楽器やマウスピース、奏法やフレーズを探求することでその片鱗を垣間見ることはできるかもしれないが、逸話の中で語られるように道具に対する執着がなかったと思わざるを得ない。楽器とマウスピースの変遷は“パーカーの個性”とは別のところに存在していたのかもしれない。そのような常に自身のスタイルを貫き続けた圧倒的な個性が、未だに多くのファンを魅了し続ける理由なのではないだろうか。
※チェンバー:マウスピースの内側の容積のこと。チェンバーのサイズは、容積の広さに応じてラージ、ミディアム、スモールがある。
※シャンク:ネックを差し込む部分の表側
Holton:Rudy Wiedoeftのモデルで有名。早くからフロントFキィを装備し、低音Cの補助音孔、G♯やHigh D♯のトリルキィなどプレイヤーのニーズに合わせた様々なメカニズムと堅実な設計を持つ楽器。
C.G.Conn:マイクロチューニングデバイスやロールドトーンホール、ダブルソケットネックジョイント等、他社に先駆けて独創的な設計を取り入れ、現在でも多くのプレイヤーに愛用されるアメリカのメーカー。
Otto Link:30年代から製造を始めジャズの黄金期を支えるマウスピースを造り続けたブランド。数多くの名演がこのマウスピースによって生まれた。
Martin:ソルダード・トーンホールによる重厚な音色がトレードマーク。欧風な感性によるデザインと設計でそれぞれの時代ごとに魅力的な楽器を送り出したメーカー。
H.Selmer:現代に続くフランスの老舗サックスメーカー。常に新しい時代に合わせた意欲的なモデルチェンジを繰り返し、操作性の良いキィ配置と洗練された音色によりモダン・ジャズの隆盛と共に爆発的にシェアを伸ばした。
Brilhart:1940年頃にミディアムチェンバーのハードラバー・マウスピースからスタートし、Ebolin、Tonalinといったプラスチックコンパウンド製でフラットサイドウォール構造を持つ新しいタイプのマウスピースを開発し、その個性的なサウンドで当時から多くのプレイヤーが使用している。
King:他社に先駆けて低音B/B♭の音孔を逆側に配置したり、アンダースラングオクターブキィ、銀製のネックやベルを採用するなどの先鋭的な設計思想と、サイドキィなどのパールインレイやキィカップへの彫刻などの豪華な装飾により、音色、演奏性、外観とすべてにおいて頂点を極めようとしたSuper20は1940~50年代に多くのプレイヤーに愛用され、多くの録音が残されている。
Grafton:プラスチックの白い管体が目を引く、パーカーやオーネット・コールマンに使用されて有名になった楽器。戦時中の金属材料の入手が困難な時期にコストを抑えて生産することに成功したが、構造上の問題で生産本数が少なく、修理が煩雑だったり、ダメージを受けて割れてしまうことが多かったりと、演奏可能な状態で現存する個体がかなり少ない。しっかりと調整をすればプラスチックの管体とは思えないファットでボリューム感のある魅力的なサウンドを持つサックスである。
Berg Larsen:1940年代から続くイギリスのマウスピース専門メーカー。当時新製品として発売したラバーマウスピースをパーカーとエンドースすることでそのブランドを世界に知らしめた。
Selmer England:イギリスの現地法人で独自の商品も製造していた。現在の流通量に鑑みると恐らく当時の生産本数も多くはなかったのではないだろうか。
Study of Parker’s Toneパーカーの音色を探る
プロ奏者が実際に体験してきた貴重な言葉を通して、パーカーの音色を探っていく参考にしてほしい。(文:池田 篤)
私が1990年に渡米した翌年くらいでしょうか、当時とても影響を受けていたアルト奏者、Jesse Devisさんから譲り受けた初めてのオールドホーンがKINGのSuper20でした。KING Super20は、ボディの管厚が薄く軽量で、軽やかに実に気持ちよく響きわたる楽器でした。それをきっかけに、私がそれまで使用していたマウスピース、Beechlerの大元であるBrilhartを試してみたくなり、最初に手に入れたのがEbolinで、軽やかに優しく響く音でした。
その後、KINGの補助の楽器として購入した楽器がCONNの6Mです。その音はSelmer Mark6以降の楽器では決して出せないようななんとも言えない深みがあり、Brilhartとのマッチングも更に良いように感じ、EbolinやTonalityなどを数本吹いた後に、ダークな音のするHard Rubberを使いました。このマウスピースはその名の通り、材質がプラスチックを含まないハードラバーです。その他のBrilhartのほとんどはコンパウンド・プラスチックでできています。
すっかりこのCONN+Brilhartの虜になり、その後もTonalin、Personalin、そしてパーカーが使用していたというStreamline(白色)にたどり着きました。この組み合わせで最良の音色を出すには、柔らかく暖かい息が必要です。しかし現代は、この楽器が生産されていた当時と比べ、バンド全体のボリュームが格段に増していると思います。バックの音量に負けないようにと大量の息を無理やり楽器に吹き込もうとすると、楽器の振動がそれに反比例してどんどん失われていくように感じました。そして倍音の成分も減り、ますます自分自身に聞こえなくなるため「さらに限界を超えて吹き込んでしまう」という悪循環に陥ってしまいました。
パーカーのアンブシュアを真似たことはありませんが、音色は常に意識してきました。私の考える最良の音色は「On Dial」でのバラードのプレイでの音です。体格、口腔内、唇、どれも人によって全く異なります。「どうすれば(方法)この音が出るか」ではなく、「この音を出すためには自分はどうしたらよいか」ということが大切なことだと思います。