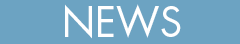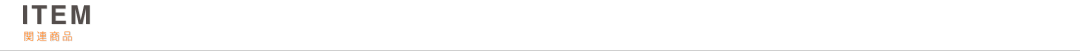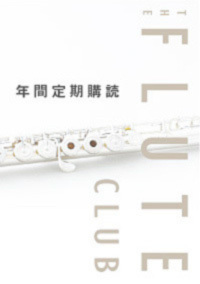ガリボルディ、アンデルセン、ケーラーを知る
エチュードの研究家としても知られている佐野悦郎氏。そのレッスンでは様々なエチュードを使用し、丁寧な解説に定評があります。そこでここでは、フルート初心者・中級者がよく使うガリボルディ、ケーラー、アンデルセンのエチュードを解説してもらいました。

佐野悦郎
武蔵野音楽大学、同大学専攻科卒業。フルートを播博、吉田雅夫の各氏に師事。ヤマハ音楽振興会にて管楽器普及のための20冊以上の多くの教本曲集等の編著に携わる。武蔵野音楽大学で教鞭を執り、日本フルート協会事務局長を歴任、尚美学園、MFLC等の講師を兼任する。その間「東京フルート・アンサンブル・アカデミー」にて海外公演(欧州、豪州、米)を実施し、多くの演奏会を開催し、それらの収録(LP、CD)を重ねた。仲間と笛属の合奏団体「四人の笛吹」を結成しアンサンブルの普及に尽力した。その他、長年に亘りリサイタル、バッロク音楽、フルートとハープ等の多くの室内楽演奏会を現在まで継続している。また、20年間にわたりムラマツ・フルートの季刊誌での紹介解説を執筆し継続中。イタリアのアルバ音楽祭(2017)に、関西の[ムジカA国際音楽協会]メンバーと教え子達「アンサンブル・ドゥ・サンクロゼ」とM.ラリュー氏、G.ノヴァ氏と共演してCD「Italhestraian Concertos for Two Flutes and Orchestra」収録し、「第31回京都芸術祭音楽部門京都市長賞」を受賞する。現在、武蔵野音楽大学教授を歴任し、同大学非常勤講師、日本フルート協会常任理事。
エチュードの重要性
「エチュードの重要性」を人体の栄養学に例えて話すと、健康維持のためには極力偏食を避け、バランスの良い栄養素を摂取することが大切と考えます。フルートの学習も同様に、練習目的は各人により様々であり、各人はその目標に向けて一気に推進し、目標に達します。しかし、一途に直進とショートカットを繰り返すために様々な基本的要素を省略し無視して突進しますので、演奏技術要素にアンバランスが生じます。そこで振り返って、基本奏法の整理が必須になると考えます。それは初級、中級学習者にとって必須で、重要です。中・上級になると振り返ることが難しくなります。その理由はある程度、何でも演奏できてしまいますから、不要に思えてしまうのです。しかし、それは自己流の始まりです。初歩からエチュード全体をバランス良く学習し、良い栄養(要素)を身に付けることが重要です。
エチュード研究に取り組んだ理由
私が「エチュードの研究」に取り組んだ理由には3段階があります。まずはじめは、半世紀前に遡りますが、当時のヤマハ音楽振興会にて「ヤマハ・フルート教室」を全国展開するために、その「テキスト、曲集」を含めて、25冊ほどを編集、編著を重ね、さらに先生方の「指導マニュアル」を著したことです。そのために世界の初歩指導教則本、練習曲を収集し、教程分析を行ないました。それが功を奏して、第2段は「音楽之友社」から当時発刊していた「フルート&フルーティスト」の記事として、フルート指導教程表、解説付きで依頼を受け、数回にわたり連載したことです。
第3段はそれを、ムラマツ・フルート「ムラマツ季刊誌」編集部が、より本格的な「フルート教程表・難易度表」の依頼を受理し、当時出版されていた世界の「練習曲120冊ほど」を全解説付きで紹介したことです。
この度、筆者は歴史的考察が重要と考え、仲間と主催している、各時代に使用していた古楽器を用いて演奏する連続演奏会『フルートアンサンブルの歴史』資料(各P.200)、【第1巻】【第2巻】概刊、現在執筆中の【第3巻】から引用し、以下の説明をしたく考えています。それは旧式楽器から新ベーム式フルートに移行していく時代の練習曲とも重なるために、各練習曲の「出版社」「初版年代」を含めて、できる限り原題で難易度表を作成しました。今までにはない歴史的、かつ学術的な教程表ですが、19世紀後半に書かれた練習曲などの初版に注目してくだされば幸いです。