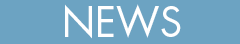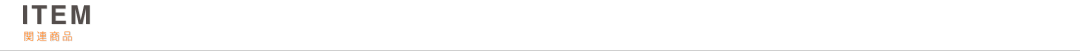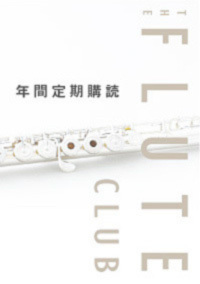練習の基本から極意まで
主にプロを目指す方やそれに準じる方が取り組む「アルテ1・2巻→ケーラー1・2巻→アンデルセンop.21・op.15→ベームop.26……etc」というエチュード「王道カリキュラム」があります。しかし、毎日練習できる環境の方には良いのかもしれませんが、お仕事や家事などで忙しくあまり練習できない、趣味で嗜む方々には、正直ちょっと苦しくなってきませんか? ということで今回は「王道カリキュラム」を敢えて外し、技術的にやさしく吹いて飽きずに楽しいエチュードを挙げてみました。これまで200人以上の初心者からの生徒にエチュードを指導してきましたが、レッスンの傾向と改善の対策は以下の通りです。
すぐに吹きたい気持ちを抑え、まずは全体を把握しましょう!
速度記号は? 表情記号は? 調性は? 途中で転調するの? テンポは変わる?etc.
フルートで吹き始める前に、まずは全体を把握することから始めましょう! 今は分厚い音楽辞典を買うこともページあちこち開いて探す必要もなく、スマホでサッと検索すればすべての情報を一瞬で得ることができる時代です。それなのに教えられるまで待つ受け身の生徒が非常に多いです。ぜひ受け身の姿勢ではなく、アクティブに曲と向き合って欲しいと願っています。
アーティキュレーションは正確に!
レッスンで多くの生徒は音を間違えないことのほうに気を取られ、ついつい無意識に「自分に都合の良いアーティキュレーション」に変えてしまい、指摘されるまでそれに気づくことはありません。そのままでも特に生徒の人生に影響することはないのですが(笑)、作曲家が書き記したスラーやスタッカートは音楽を表現する上での「命」です。ここは正確に演奏する習慣をつけるよう、「フルートは趣味なのだから」などの言い訳は問答無用で厳しく指導をしています。特に音階など音が繋がる部分では勝手にスラーが付き、跳躍などの音が飛ぶ部分では勝手にタンキングをしてしまう傾向があります。
ゆっくり練習することを怖がらずに!
「吹けないフレーズを吹けない速さで1000回練習しても、やっぱり吹けない」という事実は、こうして文字に書けば当たり前ですが、生徒のみならず私自身も無意識にやってしまっていることで、常に戒めていることの一つです。ゆっくり練習することは、アーティキュレーションや音程の正確さ、自分の音色を「自覚」することができ、メリットしかありません。発表会直前にそんなにゆっくり練習していたら本番のテンポで吹けるようにならない、と不安になる生徒もいますが、ゆっくり完璧に吹けるようになれば、そこからテンポを上げることは意外と容易です。留学時代に毎日隣の練習室からヴァイオリン奏者がモーツァルトの協奏曲を、かなり遅いテンポでメトロノームを使い延々と練習していました。後にその奏者が歌劇場のオーデションに合格したと聞き、なるほど上手い方は本当にゆっくり練習するんだな、と印象に残っている思い出です。
ブレスを出しすぎないようにしましょう!
「吹く」のではなく「吐く」息で音を当て、コンパクトながら芯ある響きを“常に”求めましょう。フルートを始めて間もない初心者は、アンブシュアを作ることも楽器を口に当てることもままならず、それをカバーするため必要以上に多くの息を使って音を出します。もちろん音が出ないフルートなんてつまらないですから、最初はそれでも良いでしょう。しかし時が経って上達し、アンブシュアの感覚や楽器を保持する技術が身に付いてきたのですから、どんどん無駄な息を減らして本来の吹き方に近づけ、理想の音を目指しましょう。
難しくて吹けない? 実は「読めてない」のかも!
技術的に難しいフレーズは、音符が混み入っていることがほとんどです。その音符のすべてを正確に読めているか、試しに一度そのメロディを同じテンポで「ドレミ」で囁いてみましょう。ソルフェージュの視唱トレーニングではないので、音程は無視して構いません。意外と口に出せないことが多く、実は「吹けない」のではなく「読めていない」ということが本当に多いのです。その証拠に読めるようになった後で吹くと、一度も吹く練習をしていないのに吹けてしまうこともあります。逆に音符が読めているのに吹けない場合、多くの先生が勧められている拍ごとや小節ごとの「部分練習」や「リズム練習」などが必須ですが、それらについては既に語り尽くされているので省きます。
試験勉強のテクニックを参考に!
受験勉強や資格試験では「知識の定着のためには難しい問題集に多く手をつけるより、基礎的な良質の問題集に絞り何度も繰り返すほうが効果的」と言われます。フルートでもこれに倣い、基礎的&良質なエチュードを繰り返すという方法に目を向けてみませんか。大切なのは「何をやったか」ではなく「何が身についたか」ということです。背伸びをして自分の演奏レベルより難しい曲に取り組む際の注意点は、無理して気合いで乗り切ろうとしてしまうことです。無駄な力が入り、音色が悪くなり、音すら鳴らなくなってしまうこともあります。生徒が新たな楽譜を見てから仕上げるまでのプロセスは、それまでの音楽経験やセンスによって一人ひとり異なり、「より高いものを目指せるが難しすぎない」教材を一人ひとりに選択することは指導者として最も気を使う部分です。
エチュードの「皿回し練習」のすすめ
皆様も学生時代、英単語を覚える際に単語帳を何度も繰り返した経験があると思います。完璧に覚えていなくても次のページに進み、また最初に戻っては復習し何度も繰り返すことを「皿回し学習」と称していました。
エチュードも同様の考えで取り組むと飛躍的にレベルアップを目指せるでしょう。例えば毎週一曲ずつ仕上げてきた一冊のエチュードを折に触れて、毎回4曲or6曲と、誰もいない練習室でも目の前に観客がいるつもりで、どれくらい間違えずに集中して最後まで演奏できるか。そんな練習ができる生徒は間違いなく伸びます。15年前に演奏旅行で来日中の世界的なプレイヤーの部屋を訪ねる機会がありましたが、デスクの上には何十年も使い込んだボロボロの『アンデルセンop.21』が置いてありました。また、コロナ禍ですべての演奏会が中止になった暗黒の時期、日本のオーケストラ奏者の皆様はご自身のエチュード演奏をYouTubeで公開されたり、自宅でエチュードに取り組むSNS投稿も多くありました。演奏力を保つ上で、エチュードの大切さを再認識する機会となったのは記憶に新しいところです。このエピソードでエチュードへの興味・関心が湧き、明日に一曲でも取り組んでみよう!と思っていただけたら幸いです。