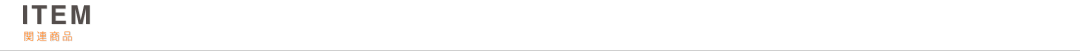[1ページ目│記事トップ]
THE FLUTE 146号 Close-Up1
若林千春 × 若林かをり
このたびCDアルバム「玉響ぴあにっシモ」を発売した現代音楽の作曲家・若林千春さん。奥様でフルーティストのかをりさんも演奏者として参加しているこのアルバムについて、146号では掲載仕切れなかったインタビューをオンライン限定でご覧いただけます。
このたびCDアルバム「玉響(たまゆら)ぴあにっシモ」を発売した現代音楽の作曲家・若林千春さん。奥様でフルーティストのかをりさんも演奏者として参加しているこのアルバムについて、THE FLUTE 146号ではお二人に話を伺いました。
現代音楽の作曲家が曲に込める思いとは? そして演奏者はどんなふうにそれを受け取り、音として表現していくのか?——インタビューの中から、本誌には掲載しきれなかったそんな話題をお届けします。

その後師となったマリオ・カローリ氏の演奏を聴き、かをりさんがどんな影響を受けたのか、千春さんの作曲のインスピレーションはどこから?……など、気になるこの続きの話題はTHE FLUTE 146号に掲載しています。ぜひお読みください!